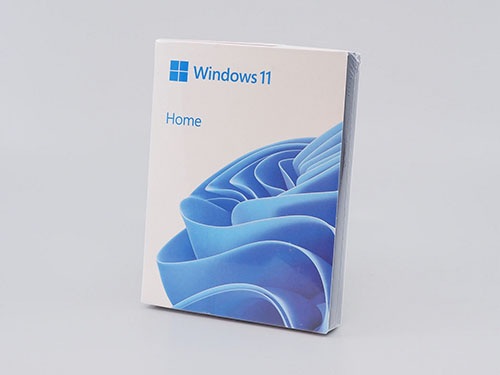特集、その他
PC初心者でも作れる!?初めての自作PC講座【ついに起動!Windows 11 インストール編】
[第4回]失敗しないための準備からの手順を画面付きで解説 text by 石川 ひさよし
2025年5月2日 10:00
自作PCの組み立てが完了しただけでは、まだPCとしては使用できません。最後の仕上げとして、Windows 11のインストールが必要です。本稿では、2025年4月時点でのWindows 11のインストール手順をなるべく詳しく解説していきます。今回、「組み立てが終わった新規の自作PCにWindows 11をクリーンインストールする」というシチュエーションの解説になります。
なお、Windows 11にはHomeやProなどのエディションがありますが、ここでは家庭用で一般的に選ばれるWindows 11 Homeを例に説明します。基本的にはProでも手順に大きな違いはありません。
また、手順の見出しに「オプション」と記載した項目は、手順としては“スキップしてもOKな工程”です。ただし、お使いの環境や状況に応じては、オプションの項目もきっちり進めたほうがよい場合もあります。内容を一読し、必要に応じて実施してください。
・Windows 11を購入する、インストールメディアを用意する
・必須のドライバやインストール先のSSDを準備する
・いよいよスタート!Windows 11のインストール
・インストール後半戦、Windows 11の基本設定や仕上げ
・[第1回]ようこそ魅惑の自作PCの世界へ!編
・[第2回]パーツの選び方と予算の基礎の基礎編
・[第3回]全手順解説!初めての自作PC組み立て編
・[第4回]ついに起動!Windows 11 インストール編 (この記事)
※自作PCの基礎知識を確認したい方は第1回と第2回を、自作PC組み立ての実践的な解説を読みたい方は第3回や第4回をご覧ください。
店舗/オンラインストアでWindows 11を購入する
Windows 11 Homeの販売形態にはいくつかあります。代表的なものがパッケージ版、DSP版、そしてオンラインコード版です。
特に自作PCではDSP版が定番とされてきました。DSP版自体は現在も販売されています。しかし、自作PCユーザーに支持されてきた理由である価格メリットはだいぶ小さくなってしまいました。また、DSP版の制限である「指定のPCパーツと同時に購入し、そのパーツと必ずセットで使用すること」、「特定のPCパーツにライセンスが紐づけられること」が後々の組み換え(パーツ交換)で足かせになる可能性があります。
そのため現在では、扱いやすさと価格の両面を鑑みると、パッケージ版またはオンラインコード版が現実的な選択肢と言ってよいでしょう。この二つを比べてみましょう。
オンラインコード版
- インストールメディアを作成する
- 購入後すぐにメール等でプロダクトキーが送付される
インストールメディアは、パッケージ版ならUSBメモリが付属、オンラインコード版はユーザーが作成します。つまりオンラインコード版はインストールメディアの作成を行うために別途PCとUSBメモリ(容量8GB以上)が必要です。
インストールメディアが付属しないならその分オンラインコード版のほうが安い……わけではありません。4月20日時点のWindows 11 Home 日本語版の参考価格を挙げておくと、パッケージ版が15,500円前後、オンラインコード版が17,500円前後です。オンラインコード版は別途USBメモリも必要なので、価格だけを見るとパッケージ版のほうがお得です。
オンラインコード版の最大のメリットは“時間”です。オンラインショップで購入すれば、決済後すぐにメールやメッセージでプロダクトキーが届きます。PCショップが閉まっている夜間帯でも入手でき、早々にインストールすることが可能です。
どちらにもメリットはありますが、本稿では、基本的に価格が安く、準備の手間も少ないパッケージ版をベースに進めていきます。
インストールメディアを作成する【オンラインコード版は必須、パッケージ版はオプション】
ここからはインストールメディアの作成方法を紹介します。前述のとおり、オンラインコード版にはインストールメディアが付属していないので、自分で用意する必要があります。
なお、パッケージ版を購入された方はこの作業が不要ですが、作成自体は可能です。たとえば再インストールが必要になった時、その間に大幅なアップデートがあると、付属のインストールメディアではインストール後に大量のアップデートをする必要がありますが、最新のインストールメディアを作成しておけば、大幅アップデート後の状態でインストールできるわけです。
“インストールメディア”とあるように、この作業にはメディア(記録媒体)が必要です。現在ではUSBメモリがお手軽なので、本稿でもこれを使って解説していきます。新品USBメモリを使わなければならないということはありませんが、USBメモリを使い回す場合、この作業によってデータが消えてしまうことに注意しましょう。
必要なUSBメモリ容量は最低8GBとされています。パッケージ版のインストールメディアの総容量は16GBで、使用されていたのは6.3GBで残り8.3GBが空き容量だったので、2025年4月時点では8GBで十分でしょう。
なお、パッケージ版のインストールメディアも普通のUSBメモリです。空き容量にファイルを追加することができます。空き容量の活用方法については後ほど紹介します。
PC初心者の方はあまり気に留めなくても構いませんが、これからメディア作成ツールで作るインストールメディアのフォーマット形式は、やや古めの規格であるFAT32になります。そのため、たとえば64GBのUSBメモリを使ってインストールメディアを作ると、32GB分がインストールメディア用の領域として利用され、残りは「未割り当て」になっていました。ただし32GB超で未割り当ての領域があっても「ディスクの管理」を使ってボリュームを作成すれば容量いっぱいムダなく活用できるので心配ありません。
USBの規格はどれでも構いませんが、速度の遅いUSB 2.0よりはUBS 3.0以上のものがよいでしょう。端子形状は、お使いのマザーボードにたいていType-Aが付いているはずなので、USBメモリもType-AでOKですが、最近はType-A/Type-C両方で使えるUSBメモリもあるので、将来性を考えるとそのような製品を選ぶのもありかもしれません。同じWindows 11 PCであればインストールメディアを使い回すことも可能です。ノートPCでも活用したいがType-Cしか搭載していない、といった時にはType-A/Type-C両用USBメモリが便利でしょう。
USBメモリを用意できたら、インストールメディア作成に関わる必要なソフトウェアのダウンロードに入ります。MicrosoftのWebページ「Windows 11 のダウンロード」(https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11)に「Windows 11 メディア作成ツール」があるのでこれをダウンロードしましょう。このツールでインストールメディアが作成できます。
「Windows 11 のダウンロード」ページには3つの「今すぐダウンロード」ボタンがありますが、今回は2つ目の「Windows 11のインストールメディアを作成する」にあるボタンを使用します。
1つ目は使用中のPCにWindows 11をインストールするためのオプションなので今回のような場合には使用しません。3つ目「Windows 11 ディスク イメージ (ISO)」はISOファイルをダウンロードできます。ISO形式はDVDに書き込んでインストールメディアとして利用できるほか、カスタマイズされたインストールメディアを作成する際にも利用します。なお、「Windows 11 メディア作成ツール」でもISOファイル形式のインストールメディアが作成可能です。
「Windows 11 メディア作成ツール」はmediacreationtool.exeというファイル名でダウンロードされます。インストールメディア用のUSBメモリをPCのUSBポートに挿した後、mediacreationtool.exeを起動してください。あとは画面の指示に従って作成作業が進みます。
ここまで進めるとインストールメディアの作成作業が開始します。ダウンロード~作成完了までしばらく時間がかかるので待ちましょう。
完成したインストールメディアはその時点の最新版(今回の場合はバージョン「24H2」)です。パッケージ版は購入タイミングにもよりますが若干古いこともあります。今回購入したパッケージ版はバージョンが「23H2」でした。